特殊車両– category –
-

特車特殊車両とは?基本的な定義と種類を理解しよう!
「特殊車両って何が該当するの?」「通行許可の申請ってどうすればいいの?」 トラックやトレーラを使用する運送業務において、特殊車両の通行許可申請は避けて通れない重要な手続きです。 しかし、「特殊車両」の定義や申請手続きの具体的な方法など、難... -

特車ゴールド制度の条件とメリット|4年許可の取得方法
特車ゴールド制度は、ETC2.0を活用し、特定の事業者・車両に対して最大4年間の特殊車両通行許可が認められる制度です。大型車誘導区間での柔軟な経路選択が可能となり、申請手続きの簡素化や費用削減にもつながります。本記事では、制度の利用条件、手続き... -

特車申請オンラインガイド2025【行政書士】
特殊車両通行許可のオンライン申請方法について、2025年の最新制度改正に対応した情報をもとに、申請の手順・準備書類・注意点を徹底解説します。「特車申請 オンライン」で検索する方に向けて、初心者でも理解しやすいよう、実務を把握する行政書士目線の... -

【図解付き】大型貨物・大型乗用の通行止め標識を見分けるポイント
質問です!下の2つの標識の違いは何か分かりますか? 標識の中に書いてある車両に注目してみてください。 左が「大型貨物自動車等通行止め」でトラックなどの貨物を輸送する車両の通行止め、右が「大型乗用自動車等通行止め」で路線バス等の車両通行止め... -

車積載はみ出し時に必要な2つの許可とは?
トラックの荷台から積載物がはみ出す場合、運行には許可が必要になることをご存知ですか?この記事では、積載物の規制や「制限外積載許可」、関連する「特殊車両通行許可」との違いや申請方法、違反リスクまで詳しく解説します。 道路交通法で定められた積... -

特殊車両の車種一覧と簡単チェックリスト
特殊車両の一覧を知りたい方へ 「自分の車両は特車?」「そもそも特殊車両ってどんな車両があるの?」通行許可が必要になる代表的な車両とその特徴を一覧で紹介します。用途別に分類し、許可要否を見極めるチェック方法も掲載しています。 特殊車両とは?... -

特殊車両通行許可の必要性と罰則リスク
「知らずしらずのうちに、うっかり違反していませんか?」 特殊車両の無許可走行は、道路損傷や事故を引き起こし、罰則の対象になることも。この記事では、道路法に基づく許可制度の重要性や、違反リスク(罰則)について詳しく解説していますので、運送... -
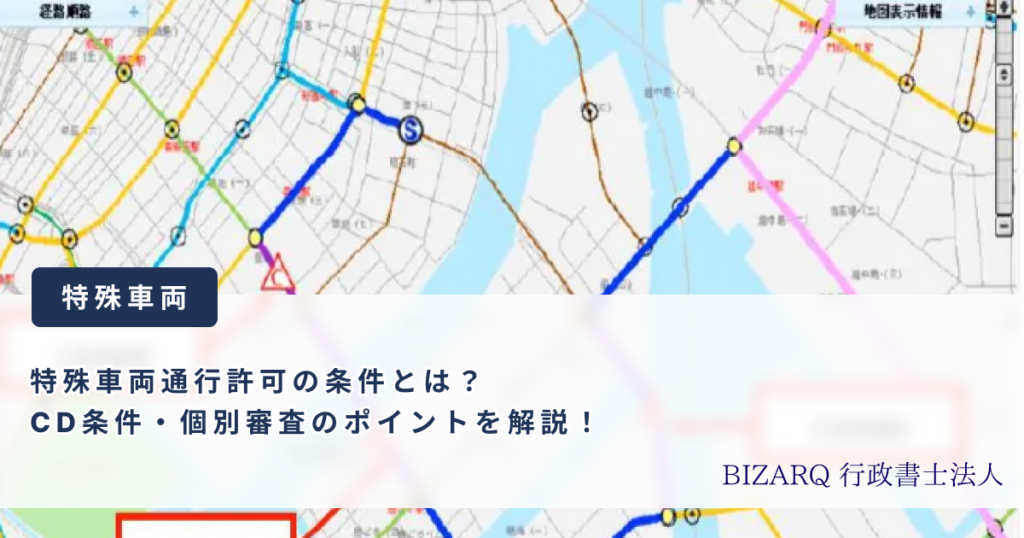
特殊車両通行許可の条件とは?CD条件・個別審査のポイントを解説!
特殊車両通行許可の通行条件について「CD条件とは?」「個別審査はどう避ければいい?」「通行条件の意味がよく分からない」など申請に必ず出てくる壁『通行条件』について解説します! その前に!▼特殊車両の「基本的な定義」から確認したい方は下記のリ...
1
