在留資格– category –
-
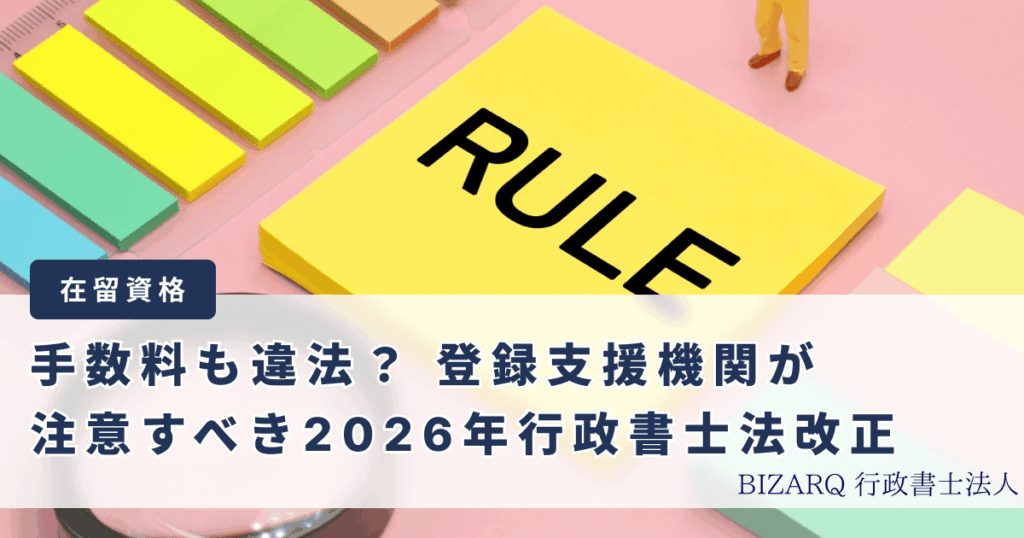
手数料も違法?登録支援機関が注意すべき2026年行政書士法改正
1. はじめに:2026年1月、行政書士法が変わります 外国人の受入れサポートを行う登録支援機関や人材紹介会社の皆様、2026年1月1日に施行された「行政書士法改正」の内容をご存知でしょうか? 今回の改正は、単なるルールの変更にとどまらず、皆様のビジネ... -

特定技能の受入を行政書士がやさしく解説
在留資格「特定技能」は、人手不足が著しい業種において即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。 特定技能外国人を受け入れるためには、複雑な申請手続きや、入国後のさまざまな支援が求められます。この記事では、特定技能制度の概要から、必要...
1
